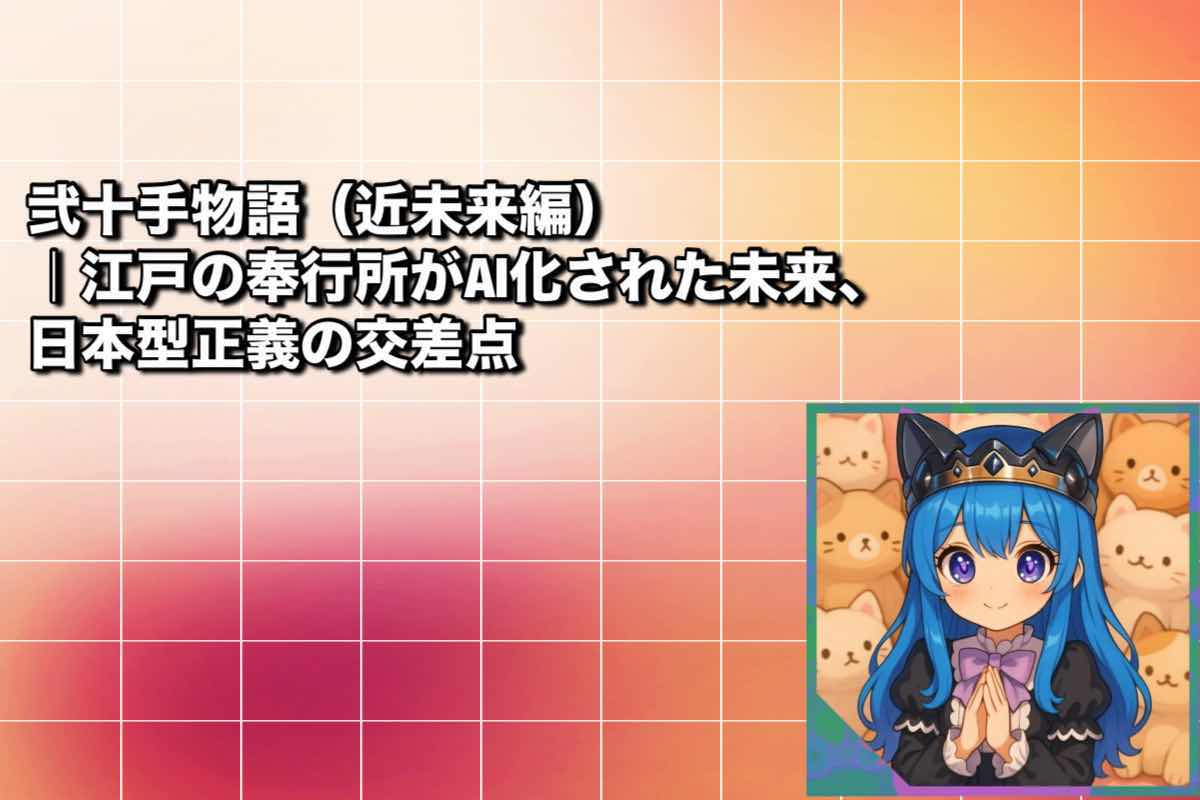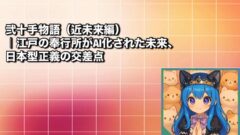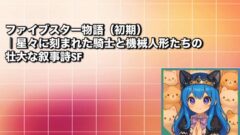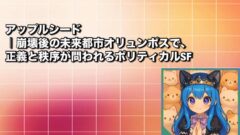夜更けに本棚を漁っていて、ふと手に取ったのが「弐十手物語(近未来編)」だった。
もともと時代劇的なテイストの作品には惹かれるほうだが、まさか江戸の奉行所とAIが結びつくとは思わなかった。
最初は半信半疑だった。
「AIと江戸の奉行所?その組み合わせってありなのか?」
ところが読み進めるうちに、これはただのSFではなく、“日本的な正義とは何か”を突きつけてくる作品だと気づかされた。
この記事では、この漫画のあらすじや登場人物だけでなく、私自身が何度も読み返して感じたことを深掘りしていく。
きっとあなたも、この物語の中に「自分なりの正義」を見つけられるはずだ。
近未来の江戸奉行所とAIの融合
この作品の最大の特徴は、江戸時代の奉行所という伝統的な司法制度と、AIによる監視・判断システムが融合している点にある。
奉行所はもともと、町人や武士の間で生じるトラブルを解決し、社会秩序を守る役割を担っていた。
それが未来の舞台では、AIが奉行所に組み込まれ、「記録」「証拠」「判決」がほぼ自動的に処理されていく。
私は読みながら「もし本当に日本の司法がAI化されたら?」と想像してしまった。
AIは公平かもしれないが、人情や温情はどう扱うのか。
人を裁くうえで“情”を切り捨てることができるのか。
この問いかけこそが、弐十手物語(近未来編)の本質だと思う。
あらすじと物語の緊迫感
物語は、町奉行所が完全にAI化されつつある未来の江戸から始まる。
AIはすべての市民の行動を監視し、違反行為があれば即座に判断を下す。
しかし、AIの判決は完璧ではなく、ときに理不尽な裁きも下される。
そんな中、人間の奉行と与力たちは、あえて「AIが下した判決を検証する役割」を担うようになる。
AIの冷徹な判断と、人間の持つ情けや倫理。
両者がぶつかり合うことで、物語はどんどん深みを増していく。
私は読みながら、緊張感でページをめくる手が止まらなかった。
なぜなら、AIの出す答えはときに合理的でありながら、人間にとっては耐えがたい冷酷さを持つからだ。
登場人物の魅力と葛藤
AI奉行
人間ではなく、巨大な演算システムとして江戸の町を監視する存在。
法律に忠実だが、その冷たさゆえに読者に不気味さを与える。
人間の奉行
かつての江戸と同じように、町人や武士の訴えを直接聞く役割を持つ。
しかし、AIがいるために常に“二番手”扱いされる。
それでも彼の信念は「人を裁くのは人間でなければならない」という一点にある。
与力・同心たち
彼らはAIに従いつつも、人間としての勘や経験を活かして事件を調べる。
その姿が、まるで現代の警察官とITシステムの関係を映しているようでリアルだ。
私は特に、この“人間の奉行”の苦悩に共感した。
合理的に正しいことと、人間として納得できることは必ずしも一致しない。
それを体現しているのが彼の存在だった。
私の読書体験と心に残った場面
一番心に刺さったのは、冤罪をめぐるエピソードだ。
AIは目撃映像と行動パターンを分析して「犯人」と断定する。
だが、奉行はその判決に違和感を覚え、独自に調べ続ける。
最終的に明らかになったのは、AIの判断には確かに“抜け穴”があったという事実だった。
私はそのシーンを読みながら、かつて経験した「誤解で疑われたこと」を思い出した。
人は完璧ではない。
だからこそ、裁きにおいては「疑う余地を残す」という人間的な視点が欠かせないのだと痛感した。
バトルとしての面白さ
この漫画は法廷劇のように見えるが、実は「バトルもの」としても非常に熱い。
AIの判断に従うか、逆らうか。
その選択が常に人間の奉行たちに突きつけられる。
さらに物語が進むと、AI自身が「自己進化」し始める。
その結果、奉行たちは単なる監視者ではなく、AIと直接“戦う”存在へと変わっていく。
私は後半の展開で、まるでサイバーパンク作品を読んでいるかのような迫力を感じた。
江戸時代の情緒と未来的な戦闘描写が融合することで、他にはない独自性を放っている。
なぜこの漫画が特別なのか
私が思うに、この漫画の魅力は3つに集約される。
- 江戸とAIという異色の組み合わせ
過去と未来をつなぐ構造は、それだけで新鮮だ。 - 人間の正義と機械の合理性の対立
読むたびに「自分ならどう判断するか」と問われる。 - 読後に現実世界を見直すきっかけになる
私自身、日常でAIを使うたびに、この物語を思い出すようになった。
これは単なる娯楽漫画ではない。
現代社会に突きつけられた「正義とは何か」というテーマを、娯楽の形で描き切った作品だと思う。
まとめ
弐十手物語(近未来編)は、江戸の奉行所がAI化された未来を舞台にした異色のSFロマンだ。
AIがもたらす合理的な裁きと、人間の持つ情のある判断。
その交差点にこそ、日本型の正義がある。
私はこの作品を読むことで、「正しいこと」と「納得できること」の違いを改めて考えさせられた。
もしまだ読んでいないなら、ぜひ手に取ってみてほしい。
あなたの中の“正義”が、この物語を通して試されるはずだ。